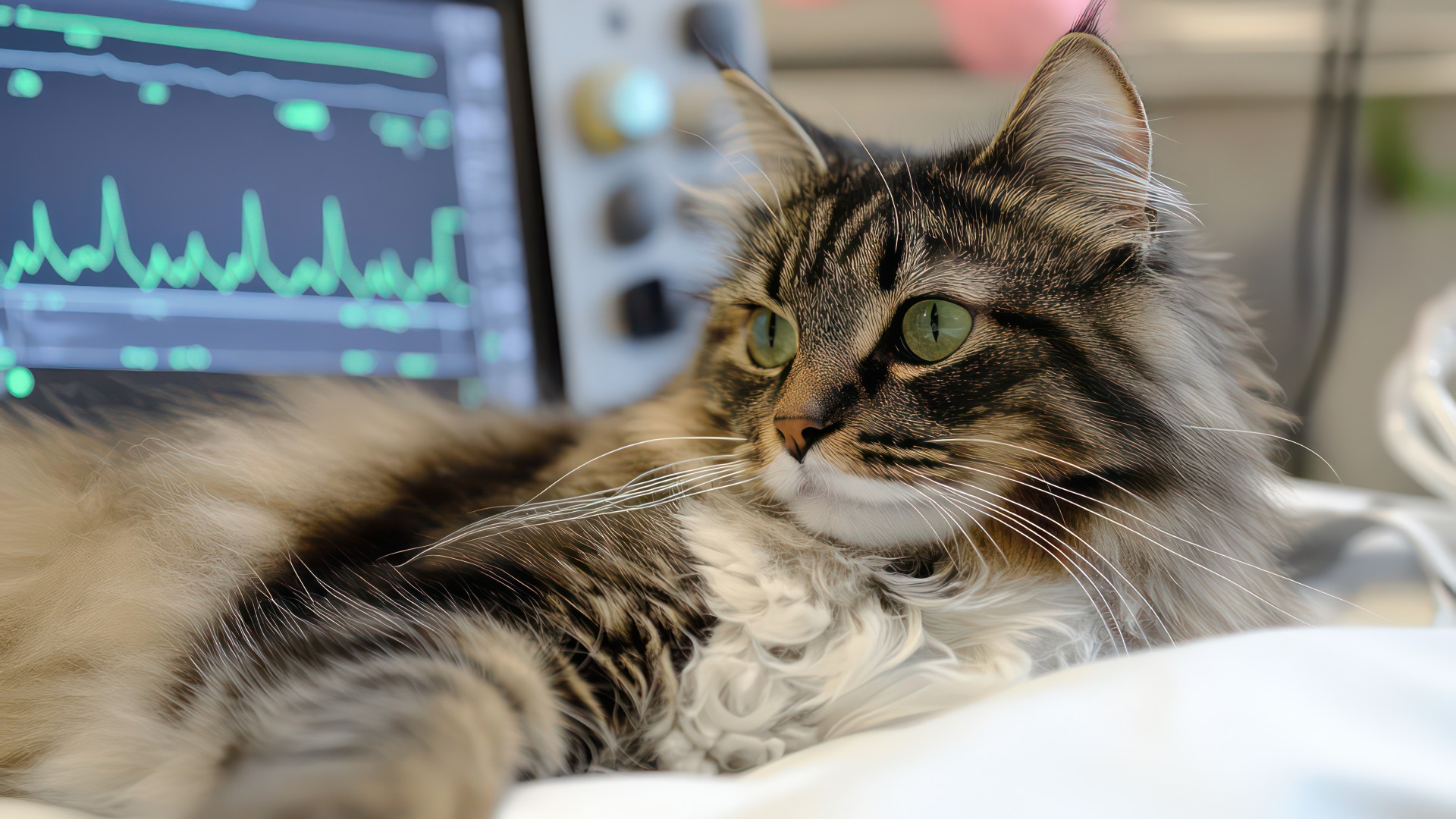人や犬と同じように猫の高齢化も進んでおり、それとともに身体のどこかにできもの(腫瘍)が見つかる子の割合は年々増えています。
今回はそんなネコちゃんに見つかる機会が多くご家族の皆さんにも注意してもらいたい腫瘍を5つご紹介したいと思います。


リンパ腫
はじめにお話するのは、リンパ球が腫瘍化して発生するリンパ腫についてです。
リンパ腫は猫で多く遭遇する腫瘍であり、消化管や腎臓、鼻腔内や胸の中(特に“縦隔”と呼ばれる場所です)、肝臓や脾臓、脳、脊髄、眼、リンパ節など、体の中のありとあらゆる場所に発生します。中でもここ最近1番多い割合を占めているのが、消化管にできるリンパ腫(“消化器型リンパ腫”と呼ばれます)です1)。
診断は主に細胞診と呼ばれる方法で、針を使って組織を少し採取し、その中に腫瘍細胞がいるかどうかを顕微鏡で確認して行います。しかし、猫ちゃんの体の外側から針が届く範囲に病変がないと、通常はこの細胞診検査を実施できません。また、切除できる場所に留まっている場合には、全身麻酔下で病変を切除し、病理検査を行うこともあります。
治療の中心は抗がん剤の投与となることがほとんどです。さらに、より多くのがん細胞を効率よく減らすために、複数の抗がん剤を組み合わせて治療する“多剤併用療法”が選択される場合も多いです。
リンパ腫は猫で多く遭遇する腫瘍であり、消化管や腎臓、鼻腔内や胸の中(特に“縦隔”と呼ばれる場所です)、肝臓や脾臓、脳、脊髄、眼、リンパ節など、体の中のありとあらゆる場所に発生します。中でもここ最近1番多い割合を占めているのが、消化管にできるリンパ腫(“消化器型リンパ腫”と呼ばれます)です1)。
診断は主に細胞診と呼ばれる方法で、針を使って組織を少し採取し、その中に腫瘍細胞がいるかどうかを顕微鏡で確認して行います。しかし、猫ちゃんの体の外側から針が届く範囲に病変がないと、通常はこの細胞診検査を実施できません。また、切除できる場所に留まっている場合には、全身麻酔下で病変を切除し、病理検査を行うこともあります。
治療の中心は抗がん剤の投与となることがほとんどです。さらに、より多くのがん細胞を効率よく減らすために、複数の抗がん剤を組み合わせて治療する“多剤併用療法”が選択される場合も多いです。
抗がん剤治療のときに気をつけてほしいこと
抗がん剤を投与しているネコちゃんのうんちやおしっこには微量の抗がん剤が含まれており、ご家族の方への抗がん剤の曝露(体に影響を及ぼすこと)が起こってしまう可能性があることから取り扱いには注意が必要です。
特に高齢の方、持病がある方、妊娠している方や赤ちゃんがいらっしゃるご家庭などは、抗がん剤を使った治療についてよく相談するようにしてください。
特に高齢の方、持病がある方、妊娠している方や赤ちゃんがいらっしゃるご家庭などは、抗がん剤を使った治療についてよく相談するようにしてください。
肥満細胞腫
猫の皮膚にできる腫瘍の中でも、多く発生するのが肥満細胞腫で、皮膚にできる腫瘍の約20%を占めていると報告されています2)。また、脾臓という古い赤血球を壊したり血液を溜める役割を持つ臓器に発生することがあり、猫の脾臓に発生する腫瘍のなかで、この肥満細胞腫が最も多いです。さらに肥満細胞腫は消化管(特に小腸)にできることもあり、リンパ腫・腺癌に次いで多い消化管の腫瘍とされます。
太っているネコちゃんが肥満細胞腫になりやすいの?
肥満細胞という名前を聞くと、太っている子にできやすいとか、体についた脂肪の存在を思い浮かべるかも知れませんが…実際は肥満とは全く関係ありません。
ヒスタミンやヘパリンといったさまざまな物質を溜め込んだ顆粒を持っているのが肥満細胞の特徴で、この細胞が増えて腫瘍化したものなのです。
ヒスタミンやヘパリンといったさまざまな物質を溜め込んだ顆粒を持っているのが肥満細胞の特徴で、この細胞が増えて腫瘍化したものなのです。
診断はリンパ腫と同じように、主に細胞診で行います。その際に顆粒を豊富に持った細胞ばかりが確認できるのが肥満細胞腫の特徴です。
肥満細胞腫の治療は外科手術で摘出することが基本となります。ただ、猫の状態や腫瘍ができた場所によっては手術が難しいことがあり、その場合には抗がん剤(化学療法とも言います)や分子標的治療薬といった飲み薬、放射線治療などが選択されます。
肥満細胞腫の治療は外科手術で摘出することが基本となります。ただ、猫の状態や腫瘍ができた場所によっては手術が難しいことがあり、その場合には抗がん剤(化学療法とも言います)や分子標的治療薬といった飲み薬、放射線治療などが選択されます。
この腫瘍で気をつけてほしいことは、細胞の中に存在するヒスタミンなどの物質が、引っ掻いたり舐めてしまって腫瘍の周りに放出される(脱顆粒と呼びます)ことです。脱顆粒が起こると、周囲の皮膚が真っ赤に充血したり、浮腫んでしまったり、ヒスタミンが過剰に猫の体を巡って胃潰瘍(胃が荒れる)を生じるケースもあります。
皮膚にできものを見つけた場合には、肥満細胞腫の可能性がありますので、ご家族の皆さんも不用意に揉んだり刺激しないようにした方が良いでしょう。
皮膚にできものを見つけた場合には、肥満細胞腫の可能性がありますので、ご家族の皆さんも不用意に揉んだり刺激しないようにした方が良いでしょう。

扁平上皮癌
猫の体のさまざまな部位に発生する腫瘍として、扁平上皮癌があります。主に耳や眼瞼、鼻、指先などの皮膚や、口の中、喉頭や扁桃、肺などに見つかります。皮膚の扁平上皮癌は、特に耳介の先端に発生することが多いです。理由としては、紫外線との関係が考えられており、毛の白い猫で特に注意する必要があります。
また猫の口の中に発生する悪性腫瘍としては、この扁平上皮癌が最も多く、70〜80%を占めているとされます3)。
また猫の口の中に発生する悪性腫瘍としては、この扁平上皮癌が最も多く、70〜80%を占めているとされます3)。
口の中の扁平上皮癌は、下顎リンパ節に10%、肺に31%転移していたという報告もあり、注意が必要です4)。
さらに扁桃に発生した扁平上皮癌は悪性度が高く、奥に存在するリンパ節に転移すると気管を圧迫して呼吸が苦しくなってしまうこともあります。
治療は外科的に切除するか、放射線療法を選択することが中心となります。残念ながら効果的な抗がん剤は報告されていません。また、口の中の扁平上皮癌を切除する場合、合併症として一時的あるいは長期的にネコちゃん自身でご飯を飲み込むことが困難となってしまうケースが多いです。そのため、手術の際に胃瘻チューブ等の設置が必要となることがあります。
そのほかの皮膚にできた扁平上皮癌であれば、完全に切除することができれば比較的予後は良好だと考えられます。
悪性腫瘍、良性腫瘍とは?
腫瘍には悪性腫瘍、良性腫瘍の2つがあります。悪性腫瘍は無秩序に増殖しながら周囲にしみ出るように広がったり(浸潤)、体のあちこちに飛び火して新しいかたまりを作ったり(転移)する腫瘍であり、臓器や命に重大な影響を与えます。
一方で良性腫瘍は浸潤や転移をせず、ゆっくりと増える腫瘍であり臓器や命に重大な影響を与えることのない腫瘍です。
一方で良性腫瘍は浸潤や転移をせず、ゆっくりと増える腫瘍であり臓器や命に重大な影響を与えることのない腫瘍です。
乳腺腫瘍
特に女の子の猫で注意したいのが乳腺腫瘍です。猫の乳腺腫瘍は皮膚腫瘍、リンパ腫についで3番目に多いとされます5)。
犬と大きく異なるのは悪性腫瘍の割合で、猫の場合は乳腺腫瘍全体のうち85〜95%が悪性であり6)、早期発見がとても大切です。
最も選ばれる治療は摘出手術です。ただ、腫瘍ができた乳腺のみを摘出する手術では、残念ながらほとんどの場合に再発してしまいます。そのため、最低でも腫瘍が見つかった側すべての乳腺切除が検討され、症例によっては左右両側すべての乳腺切除を行います。
全身麻酔下での手術が難しい子や手術を終えた子に抗がん剤を用いた化学療法を実施することもあります。
犬と大きく異なるのは悪性腫瘍の割合で、猫の場合は乳腺腫瘍全体のうち85〜95%が悪性であり6)、早期発見がとても大切です。
最も選ばれる治療は摘出手術です。ただ、腫瘍ができた乳腺のみを摘出する手術では、残念ながらほとんどの場合に再発してしまいます。そのため、最低でも腫瘍が見つかった側すべての乳腺切除が検討され、症例によっては左右両側すべての乳腺切除を行います。
全身麻酔下での手術が難しい子や手術を終えた子に抗がん剤を用いた化学療法を実施することもあります。
避妊手術で乳腺腫瘍を予防できる?
現在では女性ホルモンの存在が乳腺腫瘍の発生に関与していると分かっており、避妊手術を受けていない女の子の猫は、避妊されている女の子の猫の約7倍乳腺腫瘍が見つかるとされます7)。
ちなみに、生後6ヶ月以内に避妊手術を終えた猫では、乳腺腫瘍の発生率は91%下がり、1歳齢以下の手術では86%ほど低下するそうです8)。
おうちのネコちゃんの出産を考えていない場合は、若いうちの避妊手術について1度考えておくとよいでしょう。
ちなみに、生後6ヶ月以内に避妊手術を終えた猫では、乳腺腫瘍の発生率は91%下がり、1歳齢以下の手術では86%ほど低下するそうです8)。
おうちのネコちゃんの出産を考えていない場合は、若いうちの避妊手術について1度考えておくとよいでしょう。
注射部位肉腫
最後に紹介するのは注射部位肉腫です。
ネコちゃんのワクチン接種の際に、その接種部位にまれにしこりができることがあると聞いたことはありませんか?
その名の通り、猫の皮下に薬剤を注射したあとに発生する腫瘍であり、ワクチン以外にもさまざまな薬剤がきっかけとなるため、注意が必要です。ただ、その中でもやはりワクチンが原因となる場合が最も多く、アメリカでは1万回のワクチン接種につき1〜4例の発生率と報告されています9)。
診断において最も重要なのは、注射した部位としこりができた場所が一致していることです。通常、接種後4ヶ月〜3年経ってから腫瘍が見つかることが多いので9)、カルテ記録が大切になります。
この注射部位肉腫の治療は、手術で切除することです。
ネコちゃんのワクチン接種の際に、その接種部位にまれにしこりができることがあると聞いたことはありませんか?
その名の通り、猫の皮下に薬剤を注射したあとに発生する腫瘍であり、ワクチン以外にもさまざまな薬剤がきっかけとなるため、注意が必要です。ただ、その中でもやはりワクチンが原因となる場合が最も多く、アメリカでは1万回のワクチン接種につき1〜4例の発生率と報告されています9)。
診断において最も重要なのは、注射した部位としこりができた場所が一致していることです。通常、接種後4ヶ月〜3年経ってから腫瘍が見つかることが多いので9)、カルテ記録が大切になります。
この注射部位肉腫の治療は、手術で切除することです。
この腫瘍で知っておいてほしい点は、再発率がとても高い、ということです。そのため、なるべく腫瘍を取り除くために、腫瘍の周りを大きく切り取る必要が生じてしまいます。また、全身麻酔下での手術が難しい子や手術を終えた子に放射線療法を実施することもあります。
腫瘍が大きくなればなるほど治療が困難となりますので、早期発見がとても大切と言える腫瘍の1つです。
腫瘍が大きくなればなるほど治療が困難となりますので、早期発見がとても大切と言える腫瘍の1つです。

さいごに
猫のがんはその種類によって特に治療法や余命がさまざまです。
一昔前は、ネコちゃんが中高齢であってもあまり動物病院に連れて行く機会は少なく、今回ご紹介したような悪性腫瘍が見つかってもすでに進行していることがほとんどでした。しかし、近年では健康診断などで病院に通っているネコちゃんも増えており、早期発見されることも多くなってきています。
ご自宅でネコちゃんにしこりを見つけた場合もできるだけ早く一度、診察を受けてくことをお勧めしたいと思います。
一昔前は、ネコちゃんが中高齢であってもあまり動物病院に連れて行く機会は少なく、今回ご紹介したような悪性腫瘍が見つかってもすでに進行していることがほとんどでした。しかし、近年では健康診断などで病院に通っているネコちゃんも増えており、早期発見されることも多くなってきています。
ご自宅でネコちゃんにしこりを見つけた場合もできるだけ早く一度、診察を受けてくことをお勧めしたいと思います。
参考文献
1)Hirohumi S. et al., 2014. J Vet MedSci 76(6): 807-11
2) L Blackwood. et al., 2012. Vet Comp Oncol 10(3): e1-e29
3) A Gendler A. et al., 2010. J Am Vet Med Assoc 236(3): 319-25
4) Maria M Soltero-Rivera. Et al., 2014. J Feline Med Surg 16(2): 164-9
5) Sorenmo K.U. et al., 2013. Small animal clinical oncology. 5th ed. Elsevier Saunders, St. Louis. 547-56.
6)H M Hayes Jr. et al., 1981. Epidemiological features of feline mammary carcinoma. Vet Rec 108(22): 476-9
7)W Misdorp. et al., 1991. Feline mammary tumors: A case-control study of hormonal factors. Anticancer Res 11(5): 1793-7
8) Beth Overley et al., 2005. J Vet Intern Med 19(4): 560-3
9) K Hartmann. et al., 2015. European Advisory Board on Cat Diseases 17(7): 606-13
2) L Blackwood. et al., 2012. Vet Comp Oncol 10(3): e1-e29
3) A Gendler A. et al., 2010. J Am Vet Med Assoc 236(3): 319-25
4) Maria M Soltero-Rivera. Et al., 2014. J Feline Med Surg 16(2): 164-9
5) Sorenmo K.U. et al., 2013. Small animal clinical oncology. 5th ed. Elsevier Saunders, St. Louis. 547-56.
6)H M Hayes Jr. et al., 1981. Epidemiological features of feline mammary carcinoma. Vet Rec 108(22): 476-9
7)W Misdorp. et al., 1991. Feline mammary tumors: A case-control study of hormonal factors. Anticancer Res 11(5): 1793-7
8) Beth Overley et al., 2005. J Vet Intern Med 19(4): 560-3
9) K Hartmann. et al., 2015. European Advisory Board on Cat Diseases 17(7): 606-13